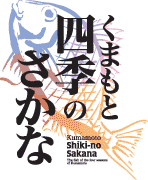 |
|
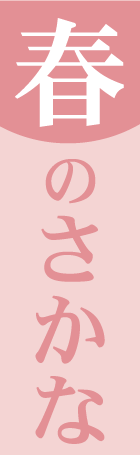 |
|
 |
| 古来より「百魚の王」として尊ばれ、お祝の席に欠かせないさかな。体は全体に赤く、鮮やかな青い斑点がある。特に春は体が桜色になり、身に脂が乗って美味しくなることから「桜鯛」と呼ばれる。県内では沿岸各所でとれる。全長約30〜100cm。 |
 |
| 干潟に生息する二枚貝。「漁(あさ)る」ことが語源。有明海は全国有数の産地で、八代や天草では「ツクシギャア」と呼ばれることもある。殻の模様は矢絣(がすり)や山形模様、放射線、波型など様々。殻のまま汁の実にすると美味で、むき身にして佃煮やぬたにも料理される。全長約4cm。 |
 |
甲の部分にさざ波状の模様があり「いかのふね」と呼ばれる石灰質の貝殻を持つ。海藻や海底に沈む木の枝に産卵する習性を利用したイカ籠(かご)漁法でとられる。肉が厚く柔らかいことから刺身のほか、天ぷらや煮物などにしても美味しい。外套長約17cm。 |
 |
| イワシの仲間で、丸みを帯びた体で銀白色の筋がある。寿命は1〜2年で、産卵は初夏。卵は岸近くの海藻に産み付けられる。キビナゴ刺し網漁や、棒受網漁でとられる。刺身や天ぷら、フライなどにして食べるほか、干物や煮干にも加工される。全長約10cm。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
